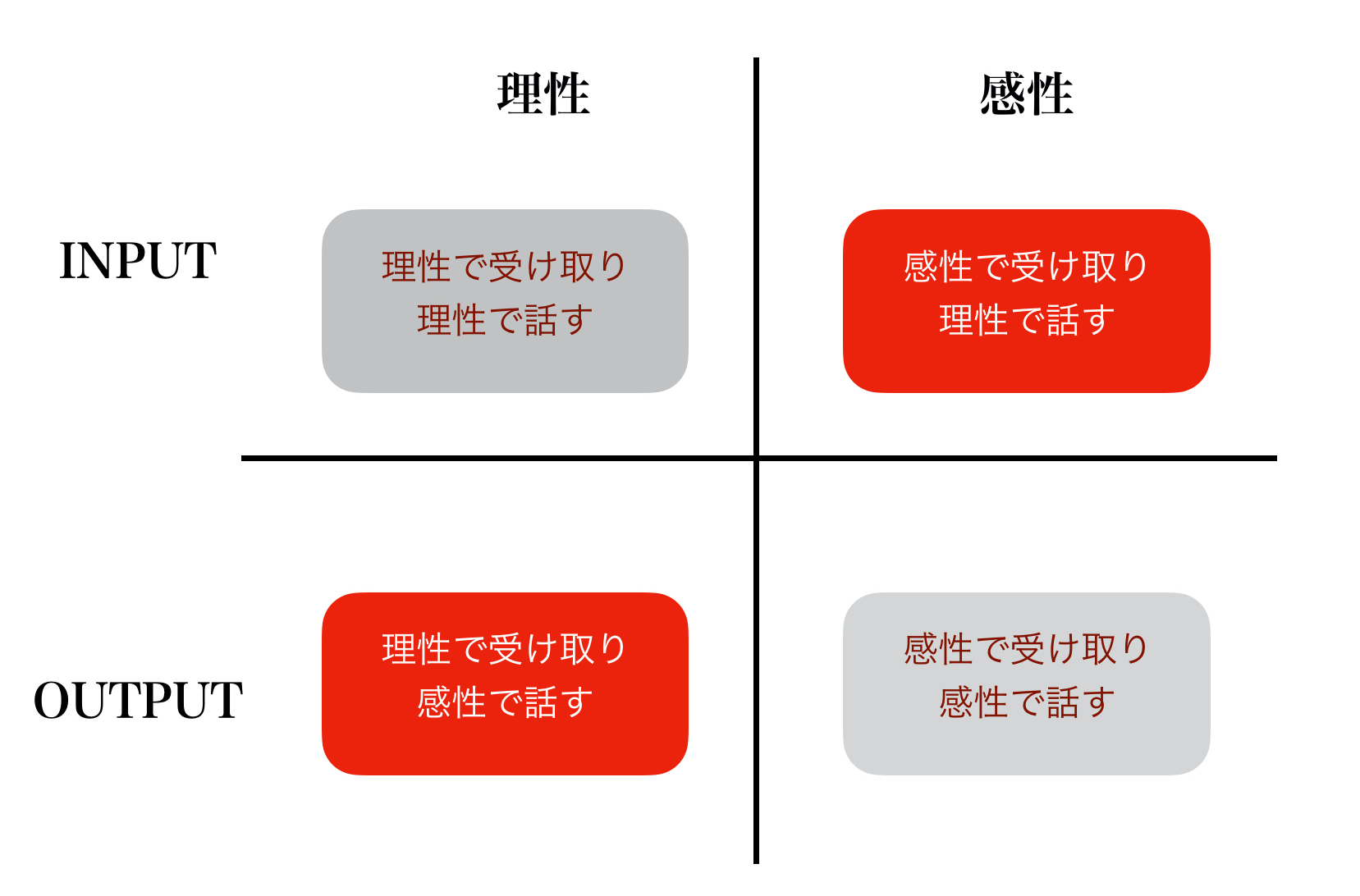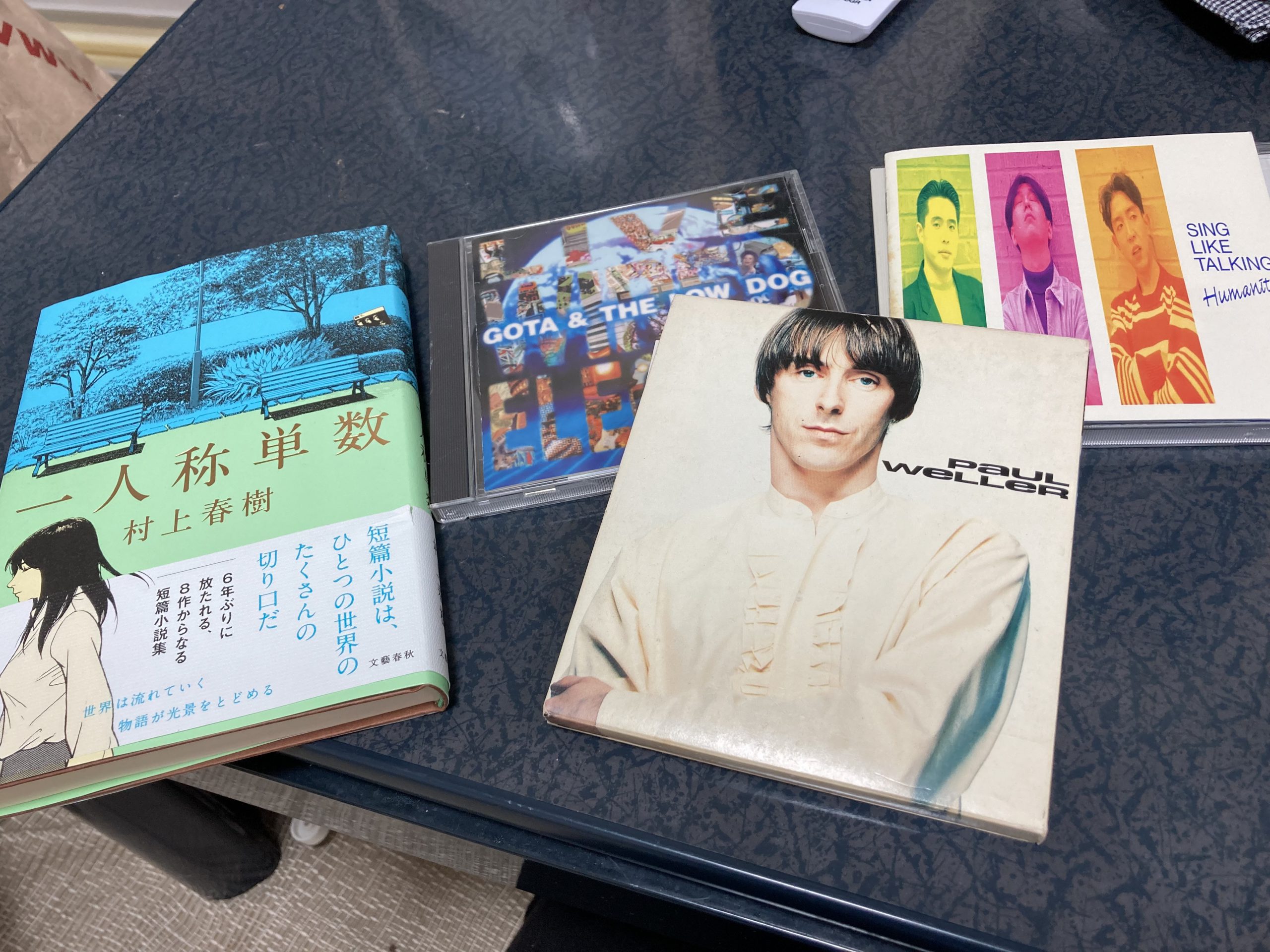寿司屋の思い出
こんにちは、暑いですね。今つくば市の気温は36度です。なんとなく空気が澱んでて、いろいろなものが霞んで見える気がします。まぁそろそろお盆だし夏本番だし、後戻りはできない、今年もこの酷暑を受け入れて生きていくしかないですね、あ、ちなみにいまiPhoneでパキスタンのカラチの気温を調べてみたらちょうど36℃でした。イスラームに改宗して、ラマダーンの習慣だけでも取り入れたいものです(基本夜に活動)。
さっきTwitterを見ていたら、寿司職人が、笑いながら手に持ったスプレーで金粉をネタや客の手やカウンターに振りかけまくってる動画が流れてきて、「なんてけしからんことをする板前なことか」と憤慨しそうになった。しかしまぁ、、、あくまで寡黙で、客の注文にもろくに返事なぞせず、黙って寿司を握り、「へい、お待ち」と、ぼそっと呟き、握りを差し出すような板前ってのはもう過去の話になってしまったのかな、とか、思った。
物価も高くなり、懐もさびしいし、すっかり寿司屋に入ることがなくなってしまったが、寿司屋っていいですよね、やっぱり。間口は狭くて、でも店前はきっちりと清められていて、夏なんかは水がキチンと撒かれている。店に入ると、まず酢飯の香りがして、それほど大きくない声で板前の「へい、いらっしゃい」の声がする。木組みの角ばった椅子に腰掛けて、おしぼりで手を拭き、とりあえず……、マグロとイカ、みたいに注文。注文なんて聞いてるのかよくわかんないくらいに、常に板前さんってのは動いている。なにやらネタを捌いていたり、下ごしらえしたエビを容器の中に詰めていたり、ほかにも色々な細かい作業を常にしている。「シェフというのは厨房で最も仕事をしている人のことだ」というのは僕の私淑する菓子職人の言葉だが、まさに板前は「常に動いている人=シェフ」といえる。そして、我々の心配をよそに、板前はちゃんと客の注文は聞いている。必ず。なので、しばらくすると「へいおまち」の声と共にマグロとイカが二貫ずつ目の前に差し出される。ネタを、わさびをといた醤油につけ、もぐもぐと食べる。うまい。次はエビとハマチかな、と思う。
***
小さい頃、住んでいた団地の近くに「やすけ」という寿司屋があった。家族でよく食べに行ったりしたし、七五三の祝いの時には二階の座敷で親戚が集まって祝いの膳を用意してもらったこともある。とても親しみやすかった店で、夜の開店前に遊びに行ったりして、見習いの若い板前さんなんかが小豆のアイスをくれたり、ガキだった僕らをよく構ってくれたりしたこともあった。ちゃんとは覚えていないけれど、子供ながらにマグロって美味しいなと思った。マクロの美味しさは、この寿司屋で食べた寿司が自分の中の基本になってる気がする。あと、玉子。ここの玉子は美味しかったな。玉子とシャリには海苔が巻かれてて、その海苔の風味もとても香り高かった。まぁなにしろ子供だったので他のネタはほとんど覚えて無いけど、母に聞いたら「あそこの穴子は本当に美味しかったのよ」と言っていた。
その後、田舎に引っ越した。高校の頃祖父が亡くなり、霞ヶ浦のすぐ近くの高台に祖父は埋葬された。その墓地の近くにある千歳寿司という寿司屋で、祖母や家族と共に食事をすることになった。店構えも妙に暗く、とてもオープンな雰囲気とは程遠い。場所も相当に奥まった所だ。「こんな辺鄙なところに寿司屋なんてあるんだな」とちょっと不思議な気持ちになったのだが、出てきた寿司は予想を超える美味しさだった。ネタは新鮮でとても大きく、シャリも大きくて、食べ応えがあった。酢飯もしっかり仕込まれていて、ほのかに温かく、ほの甘くふっくらしていた。後から聞いた話だと、住んでいた村の役場の偉い人とかの御用達として使われていた店でもあったそうだ。
蒲田に住んでいた頃は、よく東口駅前の回転寿司屋に通った。とても繁盛してた店で、常にお客でいっぱいだったが、回転のいいせいかあまり待たずに座れる。回転がいいので、レーンには活きのいい握りが常に流れていて、気兼ねなく寿司皿を取っては食べまくっていた。反対の西口側にも回転寿司屋があった。でもそこは一度しか行った事がない。残業で遅くなって東急の終電を逃してしまい、お腹も空いていたのでタクシーに乗る前に細い路地にあるその回転寿司屋に入ったのだ。もう0時を過ぎている。板前さんが手持ち無沙汰な感じで店内に1人だけいて、レーンには何も乗ってなくて(しかも半分だけしか廻してなかった)、注文したら握ってくれて、レーンに乗せて、ぼくがそれを取って食べた。こんなに寂しい回転寿司屋なんてあるんだなとその時思った。なので味がどんなだったか、ほとんど覚えていない。

 今日は、最初は丹沢に行こうと考えていたんだが、予定を変更して先日雨で行けなかった栃木の太平山に行ってきました。そこはいくつかの山が連なっているミニ山塊みたいな感じだ。太平山(341M)、晃石山(419M)、青入山(標高不明400M位?)、馬不入山(345M)が稜線でつながっていて、登ったり降りたりしながらそれらの山々を歩いてきた。まるで巨大な象の背中を歩いているような気分だった。
今日は、最初は丹沢に行こうと考えていたんだが、予定を変更して先日雨で行けなかった栃木の太平山に行ってきました。そこはいくつかの山が連なっているミニ山塊みたいな感じだ。太平山(341M)、晃石山(419M)、青入山(標高不明400M位?)、馬不入山(345M)が稜線でつながっていて、登ったり降りたりしながらそれらの山々を歩いてきた。まるで巨大な象の背中を歩いているような気分だった。 最初の太平山の頂上にあっという間に到着。頂上に来た感じもほとんどない。富士浅間神社という神社がある。社は暗い赤い色の塗壁で頑丈に封印されており、「盗難の防止のためお賽銭は入れないでください」という但し書きが貼られてあった。がらんがらんと鈴(?)を鳴らして、挨拶をして。家を出る時ちょっと寒かったので冬用のアンダータイツを履いてきてしまったが暑いのでここで脱いで、フリースも脱ぐことにした。
最初の太平山の頂上にあっという間に到着。頂上に来た感じもほとんどない。富士浅間神社という神社がある。社は暗い赤い色の塗壁で頑丈に封印されており、「盗難の防止のためお賽銭は入れないでください」という但し書きが貼られてあった。がらんがらんと鈴(?)を鳴らして、挨拶をして。家を出る時ちょっと寒かったので冬用のアンダータイツを履いてきてしまったが暑いのでここで脱いで、フリースも脱ぐことにした。 次、晃石山(てるいしやま)。まぁ、フツーの山。とりたてて感動するわけでもなく、なんか、まぁ、ここが頂上なのね、へぇ、という位。登っている間、ものすごく歌の上手い鳥がいて「ソラシド・ソラシド・・・」という上昇音型をいろんなリズムのバリエーションで歌っていた。すげえなぁ、上手いなぁ。ヴィデオに撮ったつもりが撮れてなかったのが残念。
次、晃石山(てるいしやま)。まぁ、フツーの山。とりたてて感動するわけでもなく、なんか、まぁ、ここが頂上なのね、へぇ、という位。登っている間、ものすごく歌の上手い鳥がいて「ソラシド・ソラシド・・・」という上昇音型をいろんなリズムのバリエーションで歌っていた。すげえなぁ、上手いなぁ。ヴィデオに撮ったつもりが撮れてなかったのが残念。 この辺りまで来て、だんだんと山歩きに飽きてくる。ちょっとした上りと下りが単調にだらだらと続くだけで、身体がむず痒くなってくる。山に登っているという気持ちがしてこない。そもそも今日は「低山山歩き」なので当たり前なのは分かっているのだが…。上りで身体の筋肉は一応は動き出しはするのだけど、直ぐに終わってしまうのでぜんぜん目覚めてくれない。筋肉達は「ま、普段通り適当に過ごせばええんやろ?」という日常のだらけモードのままみたいだ。ここから麓に降りることもできるのでそうしようかなとも思ったが、せっかく来たわけだし、もう一つ先の山まで行くことにする。
この辺りまで来て、だんだんと山歩きに飽きてくる。ちょっとした上りと下りが単調にだらだらと続くだけで、身体がむず痒くなってくる。山に登っているという気持ちがしてこない。そもそも今日は「低山山歩き」なので当たり前なのは分かっているのだが…。上りで身体の筋肉は一応は動き出しはするのだけど、直ぐに終わってしまうのでぜんぜん目覚めてくれない。筋肉達は「ま、普段通り適当に過ごせばええんやろ?」という日常のだらけモードのままみたいだ。ここから麓に降りることもできるのでそうしようかなとも思ったが、せっかく来たわけだし、もう一つ先の山まで行くことにする。 桜峠から晃石山に登り返す坂はなかなかの急登で、降りてくる時は何も感じなかったが、登り返しで両腿が攣りそうになる。ここにきてようやく筋肉が目を覚ましたみたいだ。後半も過ぎた今になってようやく身体が登山モードに切り替わってくれた、よかった。身体が登山モードに切り替わると気持ちも切り替わる。目だけでなく身体で山を楽しめるようになる。弾みが付いた足を使って、ずんずんと来た道を引き返す。途中で何故か頭の中でブラームスの4番が鳴り出し、脳内演奏しながら太平山神社まで一気に歩いた。ブラ4、やっぱいいなぁ、山歩きしながら感動してしまった。12時頃に神社について、フィニッシュ。車に戻って、帰宅。車中では大西順子のピアノトリオを聴く。すっげえぇ、かっこよかった。今までなんで気づかなかったんだろうというちょっとした動きとかが新鮮だった。太平山はブラームスと大西順子っていう思い出ができてよかった。
桜峠から晃石山に登り返す坂はなかなかの急登で、降りてくる時は何も感じなかったが、登り返しで両腿が攣りそうになる。ここにきてようやく筋肉が目を覚ましたみたいだ。後半も過ぎた今になってようやく身体が登山モードに切り替わってくれた、よかった。身体が登山モードに切り替わると気持ちも切り替わる。目だけでなく身体で山を楽しめるようになる。弾みが付いた足を使って、ずんずんと来た道を引き返す。途中で何故か頭の中でブラームスの4番が鳴り出し、脳内演奏しながら太平山神社まで一気に歩いた。ブラ4、やっぱいいなぁ、山歩きしながら感動してしまった。12時頃に神社について、フィニッシュ。車に戻って、帰宅。車中では大西順子のピアノトリオを聴く。すっげえぇ、かっこよかった。今までなんで気づかなかったんだろうというちょっとした動きとかが新鮮だった。太平山はブラームスと大西順子っていう思い出ができてよかった。